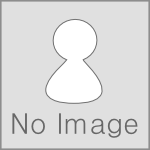「」さんのページ
9点 さよならフットボール
サッカー好きには是非読んでほしい隠れた名作。
それとこの作者は大化けしそうな予感がします。そういう意味でも注目して欲しい
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-09-03 18:27:16] [修正:2011-12-16 08:23:15] [このレビューのURL]
9点 今日から俺は!!
好きな漫画って何?
と、人に聞かれたらまず思い浮かぶのは、私はこの漫画。
基本的には肩の力を抜いて気楽に読める絵柄や内容。
だけど、時折、抱腹絶倒の切れのあるギャグや、胸が熱くなるようなぐっと来る熱いシーンも登場する。
漫画としての、緊張と緩和、メリハリは自分のリズムにぴったりだった。
ただ、5巻くらいまでは不良喧嘩漫画の出来損ないみたいな感じなので、-1点で9点。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-12-13 00:12:36] [修正:2011-12-13 00:13:44] [このレビューのURL]
9点 幽☆遊☆白書
自分にとって「名言や格言の宝庫」とも言うべき作品です。
この作品の中で、今でも強く印象に残っている言葉は以下の三点。
1 「あんたが年を取ればあたしも年を取る。それでいいじゃないか。」
2 「お前もしかしてまだ 自分が死なないとでも思ってるんじゃないかね?」
3 「できればもう一日生きたい。明日ヒットスタジオに戸川純が出る」
その他にも、この作品の中で登場している数々の名言集をかき集めれば、それこそベスト100の大辞典が編纂できるほど大量の名言集がこの作品には埋蔵されているんですが、今回はひとまず、この三つに厳選したいと思います。
その中でも特に気に入っているのが、一番最初に挙げた台詞。
「あんたが年を取ればあたしも年を取る。それでいいじゃないか。」
これは、若かりし頃の幻海師範が「老い」について悔しさを感じている若かりし頃の戸愚呂(弟)に向けて言った台詞です。
自分が年を重ねれば重ねる程、当然の事ながら周りの人達も一つ、また一つと同様に年を取っていくわけで。しかし、自分だけは変わりたくない。老けたくない。いつまでも「若さ」とか「青さ」とか、そういう若者だけが持つ専売特許を手元に持っていたい。そんな子供みたいなワガママをごねてみても、年が過ぎれば、結局はまた一つ年を取ってしまう。それは「生」を生きる人間にとって(生物にとって)悲劇そのものであり、生きる上での業、四苦八苦の四苦の一つ「老」そのものでもあるわけです。そんな生物そのものが持つ根源的な苦しみや悲しみ、怒りや不満に対して幻海師範はたったの一言で救いの手となる「答え」を提示してみせたのです。
この他にも「幽遊白書」という作品には冨樫義博という稀代の天才が生み出した珠玉の名言集が数多く掲載されているので、まだ読んだ事が無いという人にはぜひとも読んでみて欲しいと思います。なお、1巻第1話を読んだら、その次はいきなり2巻の最終話を読むか、その次の3巻を読む事をお薦めします。その理由は、まぁ個人的な好みの話なのかもしれませんが、1・2巻の内容はベタなヒューマンドラマばかりで、正直そんなに面白くありません。ですが、この部分だけで「幽遊白書はつまらない」と判断されるのは、とても忍びないので、初見の人にはぜひとも3巻以降から始まる霊界探偵浦飯幽助を読んで、「幽遊白書」を判断してほしいと思います。いやもっと言えば、「幽遊白書」が本当に面白くなるのは戸愚呂兄弟が出てきてからなので、ぜひとも暗黒武術会までは行って欲しいところです。ここまで来てしまえば、あとはもうノンストップ、勝ったも同然です。おそらく気が付いた頃には最終巻に手が伸びていることでしょう。
今こうして「幽遊白書」を振り返って、「幽遊白書」がなぜ名作と成りえたのかを考えた時、その理由はおそらく、単にキャラクターの人気やアニメのヒットによる経済的な相乗効果があったからだけではなく、こうした読む人(観る人)の心を打つ数多くの言葉たちがあったからではないかと、今になって自分は思っています。
一つの作品を読み終えた時、作中の何かに感化され、その作品によって自身の考え方や価値観が変容していく。そんな作品を、きっと人は「名作」と言うのだと思います。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-12-10 22:35:23] [修正:2011-12-11 23:40:37] [このレビューのURL]
9点 空の色ににている
芸術的かつ哲学的な作品。
緻密な描写と丁寧なストーリー展開が素晴らしい。
さすが内田氏と唸らざるを得ない。
名作ですな。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-04-14 21:51:09] [修正:2011-12-10 00:00:28] [このレビューのURL]
9点 バガボンド
やはり井上雄彦は天才かと。
画力は言わずもがなで、この世界観は自分の好みぴったりです。
序盤と比べると失速した感は否めないが、それでも低い評価にはならないですね。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-12-09 21:15:09] [修正:2011-12-09 21:15:09] [このレビューのURL]
9点 花もて語れ
朗読ってこんなに深くて熱いんだ!というのが第一印象でした。
声に出して読むことが、作品の世界観を理解し表現する上でとっても大切なんだと、素直に納得できました。こんな国語の授業を受けたかったなぁ。
音がいっさい聞こえない漫画で、朗読をどう表現するのかが一番気になっていたのですが、不思議とページから朗読者の声や作品の中で描写されている音が聞こえてくるんです。そして、いつの間にか自分も一緒に声を出して作品を朗読してしまいます。
自信なさげでいつも色々と小さくなってしまっていた主人公の花ちゃんが、朗読を通して居場所を見つけ、友達に恵まれ、次第に生き生きとしていく様子に胸が温かくなります。
花ちゃんの朗読に心打たれ、自分の悩みに素直に向き合い、また前を向けるようになっていく人たちの心の動きにも感動。
次に朗読される作品は何なのかと、今からとても楽しみです。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-12-09 17:41:31] [修正:2011-12-09 17:41:31] [このレビューのURL]
テレビドラマを見て興味を持った作品
日本のドラマでは珍しく面白い内容であったので、
漫画を手に取ったが
やはり原作である漫画の方が面白い。
医療と政治
患者と仲間
キャラクター毎に信念や目的、居場所が違う
それらを丁寧に、まとめあげられている。
まさにドラマ
人間ドラマ
是非、読んでみて下さい!
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-12-09 06:07:34] [修正:2011-12-09 06:07:34] [このレビューのURL]
9点 AGAPES
それぞれ傷を持った人間が集まって、甲子園を目指す野球漫画なんですけど、そこは山田玲司、普通ではありえない展開が目白押しで、野球漫画としてみると、ある意味ボンボンやコロコロに載っているようなけったいな作品です。
この作品を表現する言葉が思いつかないのですが、凄く良い作品です。
『Bバージン』や『NG』と根本は同じだと思いますので、「本気になれない」事を悩んでる人に読んで欲しい作品です。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-12-08 23:24:58] [修正:2011-12-08 23:24:58] [このレビューのURL]
9点 竹光侍
先日江口寿史の背景論についての議論がツイッター上で巻き起こっていたのは記憶に新しいところ。色んな漫画の描き方があるわけだけど、現在の漫画がどこへ向かっているかというと、大きな流れとしてはデジタルに向かっているのは間違いない。その程度は置いといても、全く使ってない人の方が少ないくらいかもしれない。photoshopなんかのデジタルで漫画を作るソフトが普及してきたということも影響しているのだろう。
デジタルが登場する以前を考えると、漫画とは要はペンとトーンで描かれていたわけで、漫画の進化とは画法の進化であると共にトーンが進化してきたという面も少なからずあると思う。服の柄、影、背景、様々なトーンと様々なトーンワークを漫画の中で見てきた。
でも正直な所、個人的にはトーンに惹かれたことはなかった。何でかは知らない。明らかにトーンの使いすぎでトーンが絵から浮いてたりするような漫画は論外としても、漫画としての見やすさや洗練度はともかく、“絵”としてトーンを使った絵を気に入ったことってなかったと思う。
それもこの竹光侍を見るまでということで(>前置き長いな)。松本大洋は竹光侍において、絵に専念できるということもあってか、自身の集大成のように様々な技法で絵を描いている。独特の朴訥としたタッチはもちろん、墨で描かれた大胆で迫力抜群の絵もあり、ナンバーファイブ 吾で見られた木版画のような雰囲気の絵もある。
そしてトーンの使い方。単に切って貼るのではなくて、貼った上に濃淡を変えて墨で色をつけたり、一部だけこすってかすれたような雰囲気にしたり、それらを組み合わせたり、かと思えばまっとうな使い方をしたり、あまりに変幻自在のトーンワーク。もはや松本大洋はトーンを模様として見ていない、切り絵のような、そんなもっと幅広い使い方をしている。
元々松本大洋の絵柄や技法というのは固定されていないけれど、この竹光侍の絵は場面によってころころ変わる万華鏡のようであり、“キメ”の絵ではそれらがフルに駆使されてもはや芸術とも呼べる絵を堪能できる。
アーティスティックとはまさに松本大洋のような人のことだよなぁ。既存の表現を取り入れ、さらにそれらに捕らわれずに新たな表現を模索する人だけが、新しいものを作り出せる。本当に素晴らしい。
物語はそんなに凝ったものではない。でも漫画において必ずしも物語って傑出したものである必要はないわけで。永福一成の原作は、絵を優しく盛り上げる。松本大洋の魅力は個人的に“静と動”にあると思っていて、それらを最大限に引き立てるという点で絵とこの物語はぴったりと調和している。
「とーん」と音が響き渡り、ネコはしゃべる。剣はうねりをあげて肉を切り裂く。宗一郎は鬼となって鬼と闘い、最後は鬼から解放される。美しい時代劇は美しいハッピーエンドでおしまいとなる。
それにしても何と愛おしい江戸の町とそこに住む人々。最終回では大事なものが失われてしまったようで、切なくなった。でも変わってしまうものだからこそ価値があるし愛おしいのだ、多分。読み返すと彼らはそこにいる。
竹光侍は、これ以上ない“粋”な時代劇であると共にアナログ漫画の一つの頂点だ。次に松本大洋の絵が進化するのはデジタル技術を上手く絵に取り入れた時と私は予想しているのだけど、どうだろう?…と思えばSunnyで水彩画の技法を使ったりもしているから松本大洋は油断ならない。
ナイスレビュー: 1 票
[投稿:2011-12-08 20:57:24] [修正:2011-12-08 21:28:21] [このレビューのURL]