「鋼鉄くらげ」さんのページ
- ユーザ情報
- 年生まれ(性別:男性)
- Webサイト
- http
- アクセス数
- 1114434
- 自己紹介
-
<レビュアー名の由来>
・自分を海の生物に例えたら「くらげ」だと思った。
・これだけでは何か物足りないと思い、辞書を引いて面白そうな単語を探していたところ、たまたま開いた辞書のページに「鋼鉄」という単語を発見した。
・その二つの単語を足して「鋼鉄くらげ」になった。
という単純な由来です。
<点数基準>
0―3点 つまらない漫画 嫌いな漫画
4―6点 普通の漫画
7点
割と面白いと思った作品。100点換算にすると 70 ― 79 点 評価。
世間の評価とかはあまり関係なく個人的に「面白い」と思ってしまえば割と気軽にこの点数を付ける傾向があるため、自分の7点評価はあまり参考にしないでほしいと思っている。
8点
結構面白いと思った作品。100点換算にすると 80 ― 89 点 評価。
一年に数回付けるかどうかと言う点数。基本的に続巻はここまでの点数しか付けないようにしている。7点評価との違いは、作品そのものの面白さとは別に、その作品にしかない個性や魅力、あるいは独自性のようなものがあるかどうか、という点が評価のポイントになっている。
なお、点数のインフレを防ぐために、そう簡単には8点評価を付けないようにしている。
9点
かなり面白いと思った作品。100点換算にすると 90 ― 94 点 評価。
一年に一回付けるかどうかと言う点数。基本的に完結した作品のみに付ける点数で、自分が文句なく面白かったと思う時に付ける点数。
10点
傑作と呼ぶに相応しい作品。100点換算にすると 95 ― 100 点 評価。
物語の完成度の高さが抜群であり、何度読んでも「面白い」と思える凄さが作品そのものに宿っている作品に付けている。
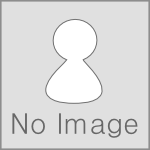
6点 ニセコイ
面白いか面白くないかという以前に、いつまでたっても「鍵の相手は誰なのか」なんていう、つまらないことにこだわりすぎている作品です。
別に鍵の相手(=10年前の思い出の女の子)が誰なのかなんて、そんな興味あるわけでもないのに、そんな些細なことで何だか最終回まで引っ張っていってしまいそうな勢いです。
少し思うんですけど、これは、いわゆる少年漫画の恋愛漫画にありがちなことなんじゃないかと思うんですが、別に「両想いになること」が恋愛漫画におけるゴールじゃない、というか、「両想いになること」をゴールだと考えている少年漫画がホント多いと思うんですよね。
両想いになる、もしくは恋人になって付き合い始める、なんて言うのは恋愛における長いプロセスのほんの節目であって、両想いになって付き合い始めたから、これから先も二人はずっと死ぬまで幸せな人生を送りましたなんて、そんな都合の良い展開なんかもちろんあるはずもなく、むしろ、付き合い始めたからこそ見えてくる新たな展開だって本当はいくらでもあると思うんですよね。
それにも関わらず、恋愛漫画、特に少年漫画の恋愛漫画は、どうも「両想いになること」を恋愛ストーリーにおけるゴールだと考えているフシがあると自分は思います。
とりあえず、「鍵の相手が誰なのか」という物語の中心事項を話の終着点として考えているのなら、悪いことは言わないので、早く終わらせてしまった方が賢明だと思います。
おそらく、続ければ続けるほど話の整合性が取れなくなると思うので。
ナイスレビュー: 1 票
[投稿:2014-04-18 22:31:18] [修正:2014-04-18 22:32:23] [このレビューのURL]
まさかの2巻打ち切りに衝撃を受けています。
実は自分、2013年の3月号を最後に、別冊少年マガジンを読むのをやめてしまったんですよね。だから、本誌が今どうなってるのかとか全く知らなかったので、今回この2巻を読んで初めて打ち切り終了を知った時は本当に驚きました。
ギャグのツボがマニアックだったり、ギャグの発想が基本下ネタだったり、明らかに別マガの、雑誌としての方向性やカラーとは少し浮いてたり、とそんな細かい減点要素はあったんですが、それでも自分は結構気に入ってました。
まぁ確かに、最後4話の話の畳み掛け方がハンパないですからね。
本誌でこれを読んでいたら「あー、もうすぐ終わるなー」と嫌でも勘づくと思います。
それにしても残念です。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2013-08-09 20:19:45] [修正:2013-08-09 20:29:39] [このレビューのURL]
6点 Rec
全16巻。124話。掲載年数10年4ヵ月。そんな長期連載を経て無事に円満終了を迎えたこの作品ですが、改めてその足跡を振り返ってみても、これと言って印象に残るものは何も無かったというのが正直な感想です。
普通の男女が普通に恋愛物語を紡いでいるような、そんな、ごくごく平凡な恋愛物語なので、結局のところ普通すぎて印象に残りません。読んでいる最中はそれなりに面白いと思ってるんですが。まぁ多分、作品そのものの「底」が浅いから読後感が残らないんだと思います。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2013-07-12 23:32:00] [修正:2013-07-12 23:42:23] [このレビューのURL]
「けいおん!」で唯たちの後輩だった「中野梓のその後」を描いたアフターストーリー。
結論から言ってしまえば「けいおん! college」よりも、こちらの方が面白いです。
何と言うか、やっぱり大学生活って、一般化しづらいと思います。学校が違うだけでカリキュラムの内容は全然違いますし、同じ学校内でも学部が違えば授業の内容だって全く別物ですから。その点、高校生活というカテゴリーは一般化しやすく、読む側も心情や体験を共有しやすい舞台だと思います。だからこそ、大学生活よりも高校生活を描いた物語の方が断然描きやすいですし、物語そのものも、ずっと作りやすいと思います。
アニメの最終回を見ていた時に、「これ、このまま唯たちが卒業すると、梓は来年一人ぼっちになってかなり寂しい学校生活を送る事になるんじゃないの?」と心配していたのですが、そうした心配がこの作品内でしっかりとフォローされていたので、その点では、意味のあるアフターストーリーだったと思います。
要点をまとめると、「けいおん! college」はダメダメなのでおすすめはしませんが、「けいおん! high school」は安心して読める続編になっています。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2012-11-09 23:49:10] [修正:2012-11-09 23:54:39] [このレビューのURL]
「自分の顔がアンパンで出来ているあの国民的ヒーローが、困っている人達へ何のためらいも無く自分のアンパンを差し出すことができるのは、パン工場で自分の顔を焼いてくれるあのおじさんが、代用品のアンパンを幾らでも作ることができるからこそ実現できる『善意』なのかもしれない」
そもそも臓器移植の何が厄介なのかというと、前述したようなお腹を空かした子供に自分のアンパンを食べさせてそれでおしまいなんていう、そんな単純な話で終わらずに、臓器を譲った提供者と、臓器を受け取った受容者の双方が臓器を担保としてお互いを新たに結び付け、これまでには無かった新たな関係性を生んでしまうことにあると考えます。
臓器提供意思表示カードに臓器提供の意思表示を示し、万が一、自身が脳死もしくはそれに準ずる状態になったとき、この臓器提供意思表示カードを見せることで、自身の臓器や皮膚、眼球などが重い病気に苦しんでいる人たちの役に立つことになる。一見するとこれは、素晴らしい話です。美しい話です。美談になります。しかし、これはあくまで「臓器提供者自身が自己完結できる部分のみを見ているから美しく見える」だけの話です。臓器移植の本当の問題は、「残された側」に生じます。例えば提供者の家族。どれだけ提供者が生前カードによって本人の意思を示したといっても、家族は常に疑念と罪悪感に苛まれ続けることになります。なぜなら、本人の口から最終的な意思確認を取ることはもう二度とできないからです。本人が一言でも「提供してもいい」と言ってくれれば、家族としても心に一切の蟠りを残すことなく、臓器提供の判断に踏みきれますが、当然のことながら臓器移植を決断する段階で本人の口からその言葉を聞くことは絶対にできません。
今回の脳死判定による臓器提供に限らず、前作の「がん編」でも末期癌患者の延命治療を望むかどうかという部分において、同じような問題は出てきました。つまり、本人の意思判断が喪失した状態で周りの人間は、どれだけ本人の意思を汲んだ決断をすることができるのか? という問題です。
「延命治療はいいから早く楽にさせてほしい」
「お金はいくらでも出すから出来る限りの延命治療を続けてあげてほしい」
今回の場合もそれは同様で、
「本人の意思に沿って臓器提供の手続きを進めてほしい」
「本人の意思には反駁するが臓器提供は行わないでほしい」
本人の意思を汲んでいるようで、実は自分自身の価値観や判断基準によって医療行為の方向性の決定意思を判断してしまう。それはとても残酷な決断であり、だからこそ普段「命」に関する方向性を絶えず判断している医師という職業は、とても大きな重責を担った職業だと思わざるを得ません。
「死」は突然やってくる。とはよく言われることですが、思うに「死」というのは、自分にとって「影」のような存在なのではないかと考えます。普段、自分の足元にある「影」という存在は、常日頃当然のようにそこに存在していますが、普段の日常生活でそれを強く意識して生活している人はほとんどいません。しかし、「影」は間違いなく今日も明日も明後日も、これから先、自分が死ぬまで確実に自分の足元に存在します。それはつまり、自分のすぐ足元に「死」という逃れられない運命が間違いなく存在していることの証左そのものではないかと考えます。
少し長くなりましたが、最後に、この作品のタイトルにある「ブラックジャックによろしく」の意味が、この「移植編」を読んで少し分かったような気がします。つまりは、技術さえあれば助かる命があるのなら、それを助けるのは医者として当然のことなんじゃないかと、それは言わば無償の善意であり、あの国民的ヒーローが差し出したアンパンそのものなのではないかと、そんなことを思います。
ナイスレビュー: 1 票
[投稿:2012-07-27 22:43:24] [修正:2012-07-27 22:46:37] [このレビューのURL]
6点 中国嫁日記
作者本人としては、20代の中国人女性と結婚した自分の新婚生活を、文化や国籍の違いから生じるギャップを含めて面白おかしく描いているつもりなのかもしれないですけど、ごく一般的な観点から至って冷静に見た場合、単なる身内自慢にしか見えないなと、そんなことを思います。
面白くないというわけでは決してないんですが、よその学校で作った卒業文集を読んで面白いと思うか、
っていうのと同じ感じなんじゃないかと思います。要するに、笑いのネタが内輪話過ぎて、「へーそうなんですか」で終わってしまう感じです。とりあえず、作品として評価するよりも、エッセイや日記の一種として捉えることの方が正解な気がします。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2012-03-30 19:38:32] [修正:2012-03-30 19:39:48] [このレビューのURL]
6点 魔法少女まどか☆マギカ
(例え話として)自分が大好きなAさんには双子のBさんがいます。そんなAさんがある時、人格だけ双子のBさんに乗り移ってしまいました。つまり、見た目はBさん、人格はAさんという人物の出来上がりです。ではここで問題です。この時私が「その人」と会話をしたとすると、果たして私は、AさんとBさんのどちらと会話をしている気分になるのでしょうか? というのがこの作品に対する感想です。
つまり、もう少し分かりやすく言えば、この作品は本質的には同じでも、その実質的な部分においてはアニメとかなりの違いを持っているという事です。具体的にその違いを挙げるとすれば、まずその「絵柄」。次にストーリー進行の細かい手順。その他にもキャラクターデザインやカット割り、あるいはアニメでしか表現できない世界観を彩る「色」、聴覚に訴える「音」やキャラクター達による「声の演技」などなど、その違いを挙げていけばキリが無いのですが、要するに、この作品がアニメと同じものだと言えるのはストーリーの骨子とキャラクターの設定くらいで、あとは林檎の芯くらいにしか本質的な部分でアニメと同じだと言えるものは残されていないということです。
ただし、ストーリーの骨子が残っている以上、そのプロットは実に秀逸です。おそらく今後十年くらいは、もうしばらくこれを超える魔法少女モノは出てこないんじゃないかと思えるくらいに素晴らしいストーリー内容です。なので、個人的には漫画ではなくアニメの方でこの作品と出会ってほしいと思います。もうインパクトというか、画面から迫りくる映像の迫力が全然違いますので。そしてその中でも特に秀逸なのが、(漫画でもアニメでも同じ)第10話。この話だけは、個人的に10点を付けているくらいに感動的な内容です。
まぁ、(アニメの方が面白い漫画に対してはいつも言ってますが)漫画はアニメを補完するためのものという位置づけでいいと思います。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2012-03-09 22:02:48] [修正:2012-03-09 22:02:48] [このレビューのURL]
6点 空が灰色だから
この作品との出会いのきっかけは本当に何でもないことで、たまたま買った別のコミックに今月の新刊情報の紙が挟まっていて、その中に、この作品のことが紹介されていた、というのがそもそもの発端です。そんな経緯でこの作品に興味を持ち、いざ実際に読んでみたんですが、これまた何とも異端というか、異質というか、とりあえず、正当ではなく、正常でもない作品だということは間違いないだろうなと。そんな事を感じさせてくれる作品でした。
何て言うんですかね。
ボケてるわけでもなく、ウケを狙っているわけでもない。
好かれようとしているわけでもなく、嫌われようとしているわけでもない。
褒められようとしているわけでもなく、非難されようとしているわけでもない。
あるのは純粋な「主張」だけ。
まるで、「これが『私』だ」と作者が作品の内側から大声で叫んでいるかのようです。
そんな作者の純粋かつ真っ直ぐで、しかも無茶苦茶な「主張」が、好き嫌いの分別や善悪倫理の判断基準を飛び越えて、作品の中から溢れ出てきているかのような作品です。とはいえ、きっと一般的な価値判断基準を持った人がこの作品を読んだら、「何この作品? 気持ち悪くて訳分かんねー」で終わってしまうかもしれません。しかし、こういった作品こそが、商業主義に染まらない100パーセント純正な「作品」の姿なんじゃないかと。そんなことを思います。
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2012-03-09 22:02:13] [修正:2012-03-09 22:02:13] [このレビューのURL]
6点 地獄先生ぬ〜べ〜
この夏に読んでみるといいかもしれない怪談漫画。
この作品が本誌に掲載されていたのは自分が子供の頃の、「ドラゴンボール」や「スラムダンク」と同じ時期だったと思うのですが、今こうして再び読んでも普通に面白いと感じるのは、結構凄い事だと思います。
やはり学校の怪談というのは、極めて普遍的でオーソドックスなテーマであり、いつの時代も変わらない不変的な面白さを持っているのかもしれません。しかし十何年も経って、改めてこうして怪談話を読んでいると、こういった怪談に対する畏怖の感情と言うのは、つまりは「未知」の物に対する畏怖の念であり、「未知」という領域、つまりは経験で補いきれない「知らない物」に対する恐怖の感情から生まれてくるんじゃないかと、そんな夢もロマンチシズムも欠片も無い感想を抱いてしまいました。当時はこの漫画が怖くて読めなかったんですけどね。ホント、可愛げの無い成長を遂げてしまいました。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-08-12 23:10:05] [修正:2011-08-12 23:17:30] [このレビューのURL]
6点 おじいちゃんは少年探偵
困った事に作者の趣味丸出しのこの作品が、
困った事に自分の趣味とかなりマッチしてしまったこの作品。
作品そのものの本質としては、割とベタな事件解決ものなんですが、4巻から5巻、物語の終盤で明かされる「物語の真実」を知った途端、これまでの1巻から3巻までで起きていた様々な事件の本質が、全く違った視点で見えてきます。
その真実が具体的に何なのかは、ここでは言えませんが、多分、結構驚くんじゃないかと思います。
あと一点。今日この日にこの作品のレビューを書いた事には、きちんと理由がありまして、その理由は、この作品を最後まで読んでもらえばきっと分かってもらえると思います。
(ヒント:今日は何の日?)
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-07-07 22:36:31] [修正:2011-07-07 22:36:31] [このレビューのURL]
月別のレビュー表示
- 月指定なし
- 2007年10月 - 2件
- 2007年11月 - 3件
- 2007年12月 - 3件
- 2008年01月 - 2件
- 2008年02月 - 5件
- 2008年03月 - 3件
- 2008年04月 - 2件
- 2008年05月 - 3件
- 2008年06月 - 3件
- 2008年07月 - 4件
- 2008年08月 - 5件
- 2008年09月 - 4件
- 2008年10月 - 3件
- 2008年11月 - 3件
- 2008年12月 - 4件
- 2009年01月 - 3件
- 2009年02月 - 3件
- 2009年03月 - 2件
- 2009年04月 - 1件
- 2009年05月 - 4件
- 2009年06月 - 4件
- 2009年07月 - 2件
- 2009年08月 - 4件
- 2009年09月 - 2件
- 2009年10月 - 3件
- 2009年11月 - 3件
- 2009年12月 - 2件
- 2010年01月 - 3件
- 2010年02月 - 2件
- 2010年03月 - 3件
- 2010年04月 - 3件
- 2010年05月 - 3件
- 2010年06月 - 3件
- 2010年07月 - 3件
- 2010年08月 - 2件
- 2010年09月 - 3件
- 2010年10月 - 3件
- 2010年11月 - 2件
- 2010年12月 - 4件
- 2011年01月 - 3件
- 2011年02月 - 4件
- 2011年03月 - 2件
- 2011年04月 - 3件
- 2011年05月 - 2件
- 2011年06月 - 5件
- 2011年07月 - 3件
- 2011年08月 - 4件
- 2011年09月 - 1件
- 2011年10月 - 3件
- 2011年11月 - 4件
- 2011年12月 - 3件
- 2012年01月 - 4件
- 2012年02月 - 2件
- 2012年03月 - 3件
- 2012年04月 - 2件
- 2012年05月 - 4件
- 2012年06月 - 2件
- 2012年07月 - 2件
- 2012年08月 - 2件
- 2012年09月 - 2件
- 2012年10月 - 3件
- 2012年11月 - 2件
- 2012年12月 - 3件
- 2013年01月 - 2件
- 2013年02月 - 4件
- 2013年04月 - 2件
- 2013年05月 - 2件
- 2013年06月 - 2件
- 2013年07月 - 3件
- 2013年08月 - 2件
- 2013年09月 - 2件
- 2013年10月 - 2件
- 2013年11月 - 2件
- 2013年12月 - 3件
- 2014年04月 - 1件
- 2014年07月 - 3件
- 2014年10月 - 2件
- 2014年11月 - 2件
- 2014年12月 - 1件
- 2015年01月 - 1件
- 2015年02月 - 1件
- 2015年05月 - 1件
- 2015年06月 - 1件
- 2015年07月 - 1件
- 2015年11月 - 1件
- 2016年01月 - 1件
- 2016年02月 - 1件
- 2016年04月 - 1件
- 2016年05月 - 1件
- 2016年06月 - 1件
- 2016年07月 - 2件
- 2016年09月 - 1件
- 2017年01月 - 2件
- 2017年02月 - 1件
- 2017年04月 - 2件
- 2017年07月 - 1件
- 2017年10月 - 1件
- 2017年12月 - 1件
- 2018年02月 - 1件
- 2018年04月 - 3件
- 2018年05月 - 1件
- 2018年07月 - 2件
- 2018年08月 - 1件
- 2018年11月 - 1件
- 2019年01月 - 1件
- 2019年02月 - 1件
- 2019年08月 - 1件
- 2019年11月 - 2件
- 2020年02月 - 2件
- 2020年03月 - 4件
- 2020年05月 - 2件
- 2020年07月 - 1件
- 2020年10月 - 2件
- 2020年11月 - 1件
- 2021年01月 - 1件
- 2021年02月 - 1件
- 2021年03月 - 1件
- 2021年04月 - 2件
- 2021年05月 - 1件
- 2021年07月 - 1件
- 2021年08月 - 1件
- 2021年09月 - 1件
- 2021年10月 - 1件
- 2022年01月 - 1件
- 2022年02月 - 1件
- 2022年04月 - 1件
- 2022年07月 - 2件
- 2022年08月 - 1件
- 2022年10月 - 1件
- 2022年11月 - 1件
- 2023年01月 - 1件
- 2023年07月 - 1件
- 2023年08月 - 2件
- 2023年10月 - 2件
- 2024年03月 - 1件