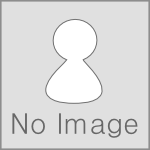「」さんのページ
6点 金剛番長
週刊少年サンデーといえばかつては「漫研部室のサンデー」とも言われたような優等生的な安心感のあるブランドだったが、近年は編集部と作家との間のドロドロした確執の話題が表面化し、雷句誠や藤崎聖人といった同誌の人気作家が他社へ移籍するなどして何とも不穏な空気に包まれている感がある。両氏とも移籍先の講談社では激しくビミョーな感じではあるが…。
そのような中にあっても、本作『金剛番長』からは、少なくともそういう不穏さは微塵も感じられなかった。作家もノリノリ、編集も輪をかけてノリノリ、互いの悪ノリが異様な相乗効果を生み、この21世紀の現代に学ラン系超人バトル番長漫画をメジャー誌で堂々連載するという究極の酔狂を貫徹、潔く「筋を通して」みせたのだから。
近年の超人バトル漫画は互いの能力や心理的駆け引きなどを重視する傾向が強いが、本作の主人公である金剛晃は「細けぇ気にするな」「知ったことかー」と居並ぶ多彩な強敵たちを次々と拳一本で粉砕していく。敵も番長、味方も番長の学ラン番外地、敗れた敵の多くは主人公の男気に惚れて仲間になり、物語演出は終盤地球規模にまで加速度的にインフレを遂げる。もう今となってはギャグにしかならないようなこれれらの意匠を確信犯的にたたきつけてくるのが本作の流儀である。作者の鈴木央はジャンプから移籍してきた過去もあり、そういう往年のジャンプ的なノリを意図していたのは間違いないだろう。
編集サイドもそんな作者の本気に最大限こたえる姿勢を示しており、単行本の帯文や巻頭巻末の煽り文句などを見ても
「せっかくだかrた俺はこの金剛番長1巻を買うぜ!」
とか
「タフすぎてそんはない」
とか
「ゲーーーーッ!?」
とか、もうやりたい放題の傍若無人、わかる奴だけわかればよし!的な酔狂が暑苦しいほどに充満していた。しまいには『キン肉マン』よろしく読者投稿による「僕の考えた番長」コンテストまで開催され、登場キャラとして採用されるなど、とにかく編集サイドの熱意が非常に感じられる作品となったのである。
ただ、このように書くと本作が悪ノリだけで構成されたような作品に感じられてしまうかもしれないが、実は結構本気で「番長」という存在の魅力を描こうとしていたのも本作の良いところだ。
物語中盤、「熱くない男は死んでよし!」をモットーとする熱血主義の化身・爆熱番長との戦いが描かれるエピソードがあるが、ここでは同じ熱血系キャラである爆熱番長と金剛番長が対比され、人の弱さも受け入れる金剛番長の度量の広さが示される。よき番長の魅力とは強さや厳しさと共に他者を受け入れる度量も併せ持った存在なのであることを改めて気付かされた格好で、作品の大半を覆う酔狂の陰で輝く真っ当さが、何とも絶妙な読後感を提供してくれた。
以上のように作品のノリとしては非常に自分の好みにあう作品だったが、しかし期待していたがゆえに残念な部分も多かったのも事実である。皮肉なことにそれらの欠点の多くはこの作品の長所が裏目に出た点が多かったのだ。
本作の魅力は単純明快で強力無比な金剛番長という主人公による部分が大きかったが、この金剛番長があまりにも強く、どんな危機に陥っても「知ったことかー」「気合いだー」で形勢を逆転させてしまうため、バトルがどうしても単調になってしまうのだ。これは近年の洗練された能力系バトル漫画を読みなれた読者には最初は新鮮にうつっても、次第に飽きられる結果となる。
また、当初は東京23区の各地区で行われていた番長達のバトルも物語の(意図された)インフレに合わせるかのように規模が拡大化し、しまいには地球を破壊しかねない勢いに膨れ上がった。むろんこれは”そういうノリ”を狙った作劇だが、さすがに酔狂だけであんな人が万単位で死んでもおかしくないような展開はちょっと…と思った。物語のラスボスである日本番長(金剛番長の兄)の悪行の動機にしても、
「母さんが愛したこの世界は母さんを拒絶した。だから俺はこの世界を憎む。」
といういかにもなセカイ系の典型で、この手の作品とは食い合わせが悪いように思い非常に萎えた。この終盤のせいで、番長漫画の復権を謳った本作が結果的に番長というイメージを風船のように肥大化させ、しまいには逼塞させたのでは?という思いもぬぐいきれない。だが、まぁそんな細けぇ事は気にせず読んで充分おもしろく、奇抜なキャラ設定のおかげでネタ漫画としても一級品の良作には違いない。単行本は全巻買う。それがせめてもの自分なりのスジの通し所だッ!
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2010-07-03 02:04:35] [修正:2010-07-04 23:01:19] [このレビューのURL]
8点 わたしは真悟
「その頃わたしはなんにも知らなくて 思えば しあわせだった」
「もう、子供の時のわたし達には会えないわ!!」
「333ノ テッペンカラ トビウツレ」
「ボクハ イマモ キミヲ アイシテ イマス」
「人間デス。」
「わたしは 三角に なった」 「わたしは マルに なった」
「これは……子どもの終わる音よ!!」
「ワタシハ イマモ アナタガ スキデス」
「そして あとに アイだけが 残った」
この作品について多くは語りません。と言うより語れません。
いや喋ることはいっぱいありすぎるのですが、まともなレビューにはなりそうもないです。
それほどまでに違う次元で構築された作品。
読んでみて下さい。 考えてみて下さい。 感じてみて下さい。
物語とはまた別の狂気を演出する扉絵も含め、とにかく「凄い」作品であることは間違いないです。
あとは読む人がどこまで受け入れるかだけ。
「これが、わたしの生まれてきた目的だったのだ!!」
わたしは真悟。 真実を、悟るもの。 真の愛を、悟るもの。
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2010-06-30 20:56:51] [修正:2010-06-30 21:05:39] [このレビューのURL]
10点 寄生獣
全十巻が足りないともだれるとも感じない、数少ない完全な作品だと思う。
環境問題や生命といったことに、作品内では登場人物が
それぞれの思想を持ち、そのどれもが否定しがたい。
ミギーの「地球は始めから泣きも笑いもしない」という台詞は読者に柔軟な思考を与えてくれる。
登場人物の心理描写も丁寧だが、わずらわしくはなく、母親のエピソードなどでは新一の悲痛な思いが良く伝わってくる。そのほかのキャラクターも個性的でそれぞれの性格が良く描かれている。
この漫画は作品のテーマ以外にもアクションシーンが見ものだ。
寄生獣同士の戦いはシンプルだがスピード感があり、迫力が感じられる。
300m離れた場所から石を投げて、体をぶち抜くという単純な攻撃が、ダイナミックで残酷かつ効果的だと感じさせる。
作品内では所々にクスッと笑える程度のユーモアもあり硬さを感じさせず、非常に読みやすい、非の打ち所の無い漫画だと思う。
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2010-06-23 04:11:55] [修正:2010-06-23 04:17:52] [このレビューのURL]
10点 風の谷のナウシカ
「映画版」が触り程度でしかなかったということを教えてくれる、映画よりも遥かに重いテーマを孕んだ「ナウシカの漫画版」。
恐るべきまでの「世界観」の構築に驚嘆の声が止まる事を知らぬだろう。
「ユーラシア大陸」で全ての事件が展開されていたことを初めて知った!
「ナウシカ」を知る人間は大きく分けて3タイプに分かれると思う。
すなわち、
・「映画版」しか観ていない。
・「漫画」しか観ていない。
・「映画」も「漫画」も観ている。
最も多いのが「映画のみ」で、最も少ないのが「漫画のみ」であろうことは容易に想像が付く。
アニメ映画の世界観が「やや分かりにくい」なとど思っていたが、漫画の複雑さと比較すれば映画は「全くもって一般向き」「間口の広い」作品であることが理解できた。
アニメと漫画の大きな違いは、
ナウシカとクシャナ・クロトアとの関係だろう。
アニメではトルメキア軍がナウシカの父を殺害してしまったことになっている(漫画では「病死」)ので、ナウシカが彼らに憎しみにも似た感情を抱いてしまい、本心からの相互理解が不可能な状況に追い込まれてしまったが、漫画では物語の大半で行動を共にするため特にクシャナ・クロトア側からの「ナウシカへの歩み寄り」が顕著。
両者共にナウシカから受ける影響で当初の「侵略者的な行動」は薄まり、苦難を共に乗り切る過程で「戦友」にも似た感情が生まれていくこととなる。
「腐海」「瘴気」「蟲」「王蟲(オーム)」「巨神兵」はナウシカの世界観を象徴する5大キーワードだと思う。
「滅亡」と「再生」。
「生」と「死」。
「光」と「闇」。
「進化」と「退廃」。
繰り返して示される背反する「2つの言葉の数々」が、浮かび挙げる「人間の業」。
そしてそれら全てを飲み込む形で存在する世界「地球」が、下す「審判の行方」。
「神によって与えられる未来」ではなく、「自らの手によって選び取る未来」を選んだナウシカたちの行く手に広がるのは「殺戮の荒野」か?それとも「豊穣なる恵の大地」か?
「審判」は未だ下されぬのだ。
とにかく1巻・1巻のボリュームが有り過ぎ。
並みの単行本の倍の時間が読み終えるのに掛かる。
不満は「恋愛的な要素」は全くというほど無かったことか。
アスベルともほとんど「別行動」となるのと、事態が急展開するため「それどころではなく」、ロミオとジュリエットにすらならない。
ま、作品の「本来のテーマ」とは外れた部分なので、枝葉のことではあるが。
最強剣士「ユパ」の死も意外だった。しかも部族同士の諍いの巻き沿いだしなあ・・・惜しい人物を失ってしまった・・・。
「漫画版」を読んだ後では「アニメ版」は「ナウシカアイドル化」のための「プロモーション作品」か?という邪推さえ浮かんでしまう問題作。
衝撃に全身を貫かれた証拠として「10点」評を献上させていただきます。
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2010-06-20 11:05:16] [修正:2010-06-20 11:05:16] [このレビューのURL]
10点 ジパング少年
●人は誰でも人生に深く影響を与えてくれた作品を持ってると思います。
それはきっと奇跡のような出合いであって、たとえどんなにいい話だとしても出合うタイミングが悪ければそうはならないだろうし、逆にどんなにくだらない話でも、その人にとっては宝物になることだってありえるのです。
この『ジパング少年』は、僕にとって奇跡のようなタイミングで出合った宝物のようなマンガです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この物語は4人の少年少女によって紡がれていきます。
皆がそれぞれ抱えているのは漠然とした違和感です。
徹底的に管理された学校。当たり前のように竹刀で殴られ、それが教育なのだと信じて疑わない教師たち。陰湿ないじめをしていたくせに停学になることだけは避けようと被害者ぶる同級生。そしてそれが認められてしまう不条理な世界。
そうした、本当は誰しも多少なりとも感じている違和感を、目一杯エネルギーに換えてひた走る、まるで暴走列車のようなお話のマンガです。
まるでそれが唯一の武器であるかのように、目に見える不条理すべてに噛み付く主人公柴田ハル。ある意味痛快ではありますが、とても危なっかしくも見えます。そんな柴田ハルにあるおじいさんは言うのです。
「世の中には2つの自由がある。“与えられた自由”の『フリー』と“掴み取る自由”の『リバティー』だよ。」
それを言われた柴田ハルはよく意味を理解出来ません。当時読んでいた僕も理解出来ませんでしたし、多分今も理解出来ていません(笑)。
ただ彼はその言葉を携えてペルーに飛んでいくのです。
ペルーは当時も今も貧しい国です。ほとんどの人が生きていくことだけで精一杯で、その国の人にとってみたら『学校の校則が厳しいから退学してこの国へ来た』なんて言ってみても誰一人理解してはくれません。彼らにとっては学校へ行くこと自体が憧れでもあるわけですから。
そんな現実に圧倒されながら彼らは想像を絶する体験をします。
学校を作るため資金集めに来た金堀り(ガリンペイロ)では、同業者に狙われたりしますし、反政府ゲリラに捕まったり、ポロロッカ(河の逆流)に攫われたり、何度も生命の危機に遭遇することになります。
しかし、それでも彼らは噛み付くのです。「それはおかしい」と。
ある時は日本の最新情報の事にしか興味のない、ペルーの日本人学校の生徒へ。ある時は視聴率以外には興味の無いジャーナリストへ。そしてある時は日本へ出稼ぎへ行って、妻を日本に殺されたと日本人を恨んでいる男に対して。
「それはおかしい」と。
主人公柴田ハルは、まるで運命に導かれるようにしてペルーのビトコス(黄金卿)を目指します。しかし多大な犠牲を払った末にたどり着いたそこには、彼が求めているような答えはありませんでした。
そこではたと気づくのです。『では一体何を求めていたのか?』と。
彼らにとってガマンならなかった『与えられた自由』とはなんだったのか。
そして長い旅を経て得た『掴み取った自由』とはなんだったのか。
それは漫画の中では明確には語られていません。
でもだからこそ魅力的だと思えるのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
僕にとってこの物語が特別なのは、柴田ハルが抱えていた怒りに賛同したからでも、社会に対して少なからず不満があったからでも、こんな風に生きたいと思ったからではありません(もちろんどれも共感は出来ましたが)。
ではなぜ特別なのかといえば『読者に対しての語りかけ』が切実に感じられたからに他なりません。
彼(作者いわしげ孝)は真剣に語りかけていたのです。日本人であることの違和感、矛盾だらけの社会、人としてどう生きるべきなのか。
そして掴み取る自由とは何を指すのか。
だからこそ、どんなに青臭いことを話していても、時代環境に合わなくなってきていても、その内容を読み返すたびに瑞々しい気持ちになるんだと思います。
ちなみに僕にとってあまりにも大事な作品であるために、読みなれることで感動が薄れてしまわないようにあんまり簡単に読まなかったりしています。
本末転倒とはこのことですね(笑)。
最後に。
このジパング少年(ボーイ)というタイトル、とても興味深いです。
直訳すると『日本の少年』。まさに日本人の今(当時)抱えている問題(イジメ、管理教育など)を提起している訳です。
そして発音は『ジパングボーイ』。これは外からみた日本人をあらわしています。この物語のほとんどが『日本人であることについて』語られているのです。
ではなぜ『ジャパン』ではなく『ジパング』だったのか。
これはマルコ・ポーロ『東方見聞録』からの引用で、日本は黄金卿だと言われていたところから来ています。つまり主人公は『日本の黄金卿』からペルーの『黄金卿』へ行った訳です。
もっともっと言えば、日本が黄金卿なのは事実なのです。少なくてもペルーの人にとっては。
日本の黄金卿からペルーの黄金卿へ。それはまるで先ほどの自由の話とも被ったりするのです。
与えられた山ほどある自由から、掴み取る数少ない本物の自由を得るというお話。
今回読み返してみて、なんとなくそんな感じがしました。
もし誰かがこれを機会に読んでみて、それで好きになってもらえたら光栄です。
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2010-06-19 22:57:01] [修正:2010-06-19 22:59:03] [このレビューのURL]
7点 幕張
「幕張」の連載が始まった1996年当時、週刊少年ジャンプは混迷の淵にあった。
ドラゴンボールをはじめとする黄金期の人気作品が次々と連載終了し、部数の低迷に歯止めはかからない。「るろうに剣心」や「封神演義」などの新たな人気作品も出るには出たが、それでも90年代初頭までの黄金時代にはなお遠い。ほどなく発行部数でもライバルの少年マガジンに一時的に抜かれたりもしたが、ともかくそんな混迷期、ジャンプもまた新たなかたちを求めて迷走をしていた。内田有紀の巻頭グラビアを載せたりしたのもこの頃だった。
しかし、そんな混迷期にこそこれまでにない新たな才能が発掘されちゃったりもするものである。後にもギャグ漫画の歴史に名を残す奇才が誌面をにぎわし始めたのだ。「すごいよ!!マサルさん」のうすた京介が、そして本作「幕張」の木多康昭が。
上記のように大げさに煽ってみたが、ではこの「幕張」という作品、万人が屈託無く笑えるお勧めギャグ漫画かというとそんな事は断じて無く、非常に人を選ぶ作品である。
・下劣な下ネタに免疫がある。
・90年代中ごろの芸能事情に詳しい。
・悪質なパロディや中傷をギャグのためなら笑って許せる広い度量。
・週刊少年ジャンプ黄金期の愛読者だった。(←最重要!)
本作を真に楽しみ、グヘヘヘと下卑た笑いを浮かべる為にはこれらの要件を満たした方がより都合が良いのだ。こうも読者層を限定するギャグ漫画、普通に考えると高評価にはならない、はずである。
おまけにこの「幕張」ときたら、ギャグの過激さが尋常ではない。タレントやジャンプの他作家を作中実名でけなすは、物語上脈絡なくオマージュどころか完全トレースしたような他作品のキャラを押し込むは、まるで青年誌のようなリアルでディフォルメを排した絵柄で、最低にもほどがある下ネタを容赦なくぶっこむは(「奈良づくし」は悪夢だった)、まぁ、本当に、ひどい。
ストーリー展開も狂っている。高校入学時、「ジャンプにはもうスラムダンクがあるから」という理由でバスケ部への入部を断念した主人公コンビは野球部に入部するが、まじめに部活動に勤しむ事など無く周りの同級生や教師たちと下品で最低な騒動をひとしきり繰り返した後、唐突に世界最強の高校生を決める「世界高校生選手権」に出場する事となり、そこでも変わらず変態的で最低な戦いを繰り広げていく…というストーリーである。最終回は唐突に「この漫画の主人公はガモウヒロシでした」と某新世界の神に喧嘩を売ってそのまま劇終という具合だった。
部活動を脇目に下品で変態的なギャグを描く、というと同時期にヤングマガジンで人気を博した「行け!稲中卓球部」が思い起こされる。ジャンプ編集部も当初はそういうノリを狙ったのかもしれないが、ふたをあけると全く違っていた。「稲中」の方は絵柄がいかにも漫画っぽく、下品なギャグの中にもどこか思春期の少年少女の葛藤みたいなテーマが描けていたのに対し、「幕張」の方は絵柄はやけにリアルで、にも関わらず真摯な裏テーマとか、そういう滋味は一切無かった。友情も努力も勝利も全ては本作ではむなしかった。
…以上のようにどうようもなく混沌とした作品だったが、それゆえに本作は当時のジャンプを象徴するメルクマールたりえたのだと今にして思う。過激なギャグを、しかし妙に浮遊感のあるシラけた描線で描いた本作の混沌っぷりは、そのまま冒頭にも書いた当時のジャンプの混迷の表れだったのだ。
原哲夫、宮下あきら、こせきこうじ、北条司、鳥山明、井上雄彦…、かつて木多康昭が深く愛した大作家達が次々と疲弊して一線を退いて行く。次のスタンダードも未だ確立はされない。
そんな中、ギャグ漫画としての行儀の悪さというある種の治外法権を最大限に発揮する形で「幕張」は当時のジャンプのネガ面での象徴となり、ふがいない同誌の現状に対する嘲笑ともなり、同時に去り行く黄金時代への惜別の弔鐘をかき鳴らしたのだ。本作にやたらとドラゴンボールとスラムダンクのパロディが頻発する事もそれを物語る。こうしてひとしきり毒を吐き散らした後、作者は敬愛する井上雄彦の後を追うように講談社へと移籍を果たし、現在に至っている。
当時の特殊な状況の生んだ鬼子のような作品には違いないが、「幕張」というほかに類を見ないギャグ漫画の事を忘れることは多分無い。ジャンプの歴史に良くも悪くも刻み付けられた凶悪な爪跡なのだ。
なお、下ネタ・内輪ネタ・過去作のパロディなどの本作の得意としたギャグのエッセンスの多くは、現在のジャンプ漫画では「銀魂」に受け継がれている気がする。
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2010-05-25 00:23:57] [修正:2010-06-10 23:30:05] [このレビューのURL]
7点 少女ファイト
夢中になって読める作品であることは間違いありません。キャラはみんな愛すべき存在だし、バレーボールの試合の描写も丁寧かつ適切でさらに魅力的。極めて狡猾(ほめてます)な複線張り方とその回収のスピードの速さ。忘れ難いメッセージ性も適所に孕んでいます。
でもなんだろう、巻を進むごとに感じるようになるこの違和感は。おそらくキャラがみんな作者のコントロール下にあることに対する嫌悪感を拭えないんですよね。
あたりまえっちゃあたりまえ。批判の対象になることすらおかしいのかもしれませんが、この作者の作品はその欠点が露骨に出てしまっていることが多いのではないかと思わされます。あまりにもキャラの動きに、作り手の作為が感じられる。感じさせない作品の方が稀有なのでそれを求める方が我侭なのかもしれませんが。
『G戦場』なんかにも見られる特徴ですが、物語の中にいる人々だけで人間関係を完結させていることへの嫌悪感が残念ながらこの作品でも感じられるようになってしまったことが残念で仕方ないです。
5巻までは満点に限りなく近い漫画だったんですが・・・。これからの展開に期待しながら、見守っていきたいです。
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2010-02-17 22:32:27] [修正:2010-06-09 18:42:43] [このレビューのURL]
10点 寄生獣
10点満点ですが、10万点ぐらい評価したい作品です!
他の漫画と比べられないぐらい群を抜いて凄い漫画です。
100回以上繰り返し読みましたが、未だに「寄生獣」の
すべてを理解出来てないと思います。
本当に濃厚で奥が深く考えさせられる作品です。
数多くの漫画を今まで読み、漫画に関して言えば辛口な私ですが
「寄生獣」は文句の付け所がない完璧な作品だと思います。
たまに、絵が下手など言う方がいますがどこが下手なのでしょうか?
もっとたくさんの方に読んで欲しいし、もっと評価されて欲しいです。
まだ「寄生獣」を読んでない方、必ず読んで下さい!!!
最後まで読んだ後、あなたも「寄生獣」の虜になることでしょう。
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2010-06-06 03:03:45] [修正:2010-06-06 03:03:45] [このレビューのURL]
10点 めぞん一刻
この漫画が他の高橋留美子漫画と一線を画しているのは、モラトリアムから脱却している点にあると思います。
うる星、らんまのように「るーみっくわーるど」と総括される世界があり、そこを舞台に毎日を楽しくドタバタと過ごし、新キャラは大抵誰かの関係者、その狭い人間関係内で誰かと誰かがいい感じになったりする。
このいつも変わらず安心できるテーマパークのような特徴は魅力でもある一方、閉鎖的、保守的なモラトリアムだとたびたび揶揄されてきた点でもあります。
このめぞん一刻は一見そういったいつものパターンを踏襲しているようでありながら、実は結婚という確実な終末が初期の段階から明確、という大きな違いがあります。
さらにこの漫画は連載時間と漫画内の時間が連動しており、キャラは歳をとります。ここも他作品と大きく違う点です。
21だったヒロインは最終的には28になり、ダメ学生だった主人公は物語が進むにつれ明確に「成長」します。
この漫画は結末に向けての二人の成長物語でもあるのです。
この漫画の最終回を読み終えた時、ずっと続くはずの物語が完全に終った事を告げられ、読者はここで強制的に作品世界から追い出され、莫大な喪失感を抱えます。
それは一刻館というよりも、この漫画そのものがモラトリアムだったからだと思います。
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2008-07-17 23:31:41] [修正:2010-06-05 18:06:53] [このレビューのURL]
10点 ONE PIECE
壮大なストーリー、幾重にもめぐらされた伏線、もはやバトル漫画というよりストーリー漫画というほうが良いのでは?ってくらい深い漫画です!
中には、バトルシーンが長いとかストーリーが長いとか言う人もいるけど、別に引き延ばしてるわけじゃなくて逆にどんどん質を上げてさえいる作品だと思います。
特にバトルシーンに関して言えば尾田さんは読者の興奮を大切にしているので丁寧に書いているのだと思います。
僕はバトルもストーリーも長いとは全然思いません。
世界で一番売れている漫画の実力一度手にとって読んでみてください。
ナイスレビュー: 2 票
[投稿:2010-06-04 15:15:14] [修正:2010-06-04 15:15:14] [このレビューのURL]