「あおはな」さんのページ
- ユーザ情報
- 1976年生まれ(性別:男性)
- Webサイト
- http://
- アクセス数
- 136915
- 自己紹介
- お気に入り漫画が次々に完結して少しシュールだなとおもいきや、また新連載が次々に開始されて・・・あーよかった。最近はそんな毎日です。
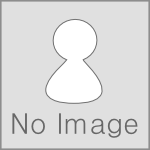
8点 ヴィンランド・サガ
正直、4巻までは何度かリタイヤしそうになったのですが、それ以降、特に王子登場のあたりからとても面白くなってきました。
現段階でのポイントは4巻、6巻、8巻くらいでしょうか。
幸村先生の作品は個人的にはいつもなのですが、「つかみで衝撃をうけてそのままよんでいくタイプではない」ようなので、1巻、2巻くらい読んで続きを読んでみようかなとお考えの方には幾分入りにくいように感じます。
海賊系の漫画と言えば、本作、ワンピース、フルココがありますが、個人的には本作が一番完成度が高いと感じています。
まあジャンルは一緒でも、各々タイプは全く異なる作品なので比べるのもおかしな話かもしれませんが。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-02-03 09:45:05] [修正:2011-02-03 16:39:08] [このレビューのURL]
8点 キャプテン
私の場合、アニメ版から入ったのでキャプテンが2代目に代替わりしたアタリの印象までが最近まで強かったのですが、最近機会があり再読してみるに、五十嵐編が自分の中では一番引き込まれました。
しかしこれでもかというくらい野球。熱い。でも読める。ある意味すごい。
意外な発見に高めの点数
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-02-02 22:53:12] [修正:2011-02-02 22:53:12] [このレビューのURL]
9点 まんが道
あえて誤解を恐れずに言えば、漫画読みを語る上で本作をはずすわけにはいかない。そういって過言ではない作品。
マンガ「学」なる研究ジャンルさえも確立されつつある現状から考慮すれば、本作はもはや娯楽作品としての枠を超えてすら評価されるべきレベルに達してしまったのかも知れません。
本作を読んでいると、手塚先生はいかに敬愛されていたかを知ることができるし、またそれだけの人物であったことも然りで、目頭が熱くなる瞬間もあります。
個人的に本作品は十代の人に読んでもらいたいなあ。
理由はあえて書きませんよ。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-02-02 19:50:23] [修正:2011-02-02 19:50:23] [このレビューのURL]
8点 BECK
音楽漫画では個人的には最も完成度が高い作品だと思います。
映画化されたけれど、コレはのだめと異なりまさに漫画でこそ面白い作品です。
なんでかというと本作品は「音が分からない」「コユキの声が分からない」ところがほんとはポイント。
のだめの場合はクラシックですでに「音源がある」から映像化しても崩壊しない(どころか映像化したほうが良いタイプ)なのに対してBECKは「音源が無い」ので「この音、あるいはコユキの声どんだけすごいんだよ」ということを「個人の想像力で補う」タイプなわけで、本当は映像化に最も適さないまさに漫画が漫画である所以を体言したような漫画。
漫画で読まなければ意味が全く無いんです、ホントはね。この手の漫画に偏見がある人(実は私)もぜひ。意外と漫画の深さを知ることができます。
ナイスレビュー: 1 票
[投稿:2010-11-03 20:35:15] [修正:2011-02-02 19:39:21] [このレビューのURL]
6点 ONE PIECE
この漫画少年誌の制約上主張できない哲学性をギリギリで随所にちりばめているのが分かる時だけビビッドにきます。
例えば空島へいく直前のクロひげとルフィの初対面のシーン「人の夢は終わらねぇ」の見開き周辺の話(ベラミーとの対比)の話は少年誌的にはギリギリの表現をしたなとおもいました。
ああこの人、実は井上雄彦先生とか王欣太先生と同じ様な考えを持っているのだなと。少年誌ではここが限界なんでしょうね
そういう葛藤と戦っているのでしょね。
もうお話的にはおなか一杯なんですけど、そういうところに敬意を表してこの点数で。
追記・頂上決戦が終わってからの展開に不満。
料理人のネタがマジネタで運んだことに「冷えた」
よって一点下げました。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2010-11-04 17:24:11] [修正:2011-02-02 19:36:06] [このレビューのURL]
面白いか否か以上に本作品は「現代的」な漫画だなと思います。
そういった意味で高めの点数。
何が?
まずこの作品あえて監督のタッツミーが主役なんですが、実際少年誌なら間違いなくバッキー(椿)が主役で運んでいっても良いところをあえて辰巳にしているところ。
この傾向はキングダムやセンゴクなど最近の青年誌系によく見られる主流になりつつある傾向という意味で現代的。(この三作品傾向が良く似ている)。
次に各キャラにかなりストーリごとに焦点をあてる「誰が主役やねん」傾向も現代的(この手の作品本当に多い)。
とはいってもこの傾向の中では辰巳と椿の主役裏主役のラインが決して喰われることがないという意味では本作は完成度が高く洗練されていると思います。
おそらくセンゴクやキングダムと異なり「監督が主役」というところに視点が過剰に釣られがちで多くのものを見落としやすいので人によって評価がまちまちになるのは仕方ないなと感じます。
でも新しい。新しいと感じないレベルで新しいところが。
多分この漫画の評価が定まるのはだからもっともっと後なんだろうなあ。途中で辰巳の回想シーンで丸々1巻消費した時だけはやや危ないかなとおもったけど。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2010-11-04 20:44:23] [修正:2011-02-02 19:32:22] [このレビューのURL]
8点 フリージア
どうも結構この作品も難解なのでしょうか?
松本次郎先生の作品の中ではかなり理解しやすい部類には入るはずなんですが、やはり単なる「小ネタ」を織り交ぜた雰囲気漫画と捉えられる傾向があるような・・・
とはいってもこの作品は「シマウマ」の話を前面に出している段階でかなり先生の作品では分かりやすい部類です。
シマウマ=擬態。叶くんをシマウマと表現する溝口の会話。
意思の効力(功罪か?)そしてラストシーンへ繋がるあの流れ。
よく読むとちゃんと繋がっているんですが、なんか難しい。
このアタリが楽しめるかどうか?コレ次第では本作はDQNの愉快な殺し合いとウッシー小山とミータの小ネタ劇場で終わるかもしれませんが。
意思がない=感情の振幅がない=目立ちにくい=擬態しやすい。そして意思を持つことは擬態が・・しにくい。敵討ち戦で様々な人間に疑問を持つ叶が最後は・・・そして・・普通と思っている事柄が異常で異常と認識されていることが意外とそうではないのかも?という循環。この漫画の妙味なのかでしょうか?
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2010-11-04 20:27:45] [修正:2011-02-02 19:30:30] [このレビューのURL]
8点 ぼくらの
この作品は「2度」読むことを半ば「強要」しているという意味で「深くて傲慢な漫画」だと思います。
この漫画の主人公は子供全員と言えばいえなくもありませんが、実は明確に「中核」になる子がいます。
そしてその中核の子が誰かを認識した上でないと途中で戦っていく子供たちのうち少なくとも10人を通して語られる主張哲学が明確にならないという意味で2回読まないと理解できないつくりになっている(この点はすごいと思う反面立腹)。
タイトルが「ぼくらの」。「ぼく」とは誰かということです。
これ11巻の圧巻の表現技法からなる最後のあの子のラストシーンでさりげなくもはっきりとカミングアウトされています。
1巻の衝撃のラストに加担するのが何故かれでなければならなかったのかという時点で本作を描いている段階であの子をラストにしようなどというやっつけ仕事でもないのは明らかで、本作はなるたるに比べて非常に完成度が高く洗練されています。
いや洗練されすぎていてそっけなく味気なく感じるほどに。
細かいところに気がつかないと「またガキが死んでいくあの展開か?」でおわってしまうので残念。
それを考慮してかアニメでは上記で述べたことに気がつかなくても良いようにまさにこの部分に関連していくところのみに大幅な「改変」が行われまして、「二人の妹」に関する話が完全に飛んでしまいました。
この漫画で表現上最も評価すべき11巻のあのラストシーンがなくなってしまったわけで、漫画で読まないと意味が無い作品の筆頭に上がります。
アニメ化にあたってアニメ監督の森田宏幸さんは「子供を助けたい」と鬼頭さんに「改変」許可をもらうにあたって鬼頭氏は「魔法を使わないならばOK」と答えたそうです。
この回答にも深い意味あります。「死んで生き返る展開はやめてくれ」と暗にいっているわけですから。
それにしても最近、読解力を求める漫画増えました。漫画を読む年齢層にあわせると必然的にこうなってしまうのかわからないですが、IKKI、エロティックF、アフタヌーン、イブニング、スピリッツとモーニングの半分以上はこの傾向が強い。漫画は日々色んな意味で進化していると感じる反面、単純な娯楽性は逓減していくわけで複雑でもあります。
ナイスレビュー: 1 票
[投稿:2010-11-05 16:50:53] [修正:2011-02-02 19:28:56] [このレビューのURL]
8点 シガテラ
作風フルモデルチェンジを果たした古谷先生の2作品目。
完成度はヒミズのほうが高いのかもしれませんが、この作品の意味合いは他にあると思います。
「なるたる」「ぼくらの」のレビューでも触れたのですが、この作品などで述べられている主義哲学を暗に主張している作家さんは事のほか多く、それを「志向・狂気・粋・美学」の形に置き換えて通常表現されていて一見するだけでは気がつかない(というより気がつかなくても楽しめる)ようにしているのですが、鬼頭先生と古谷先生はそれを主張しただけでなく「自分はその価値観についてこちら側のスタンスをとる」と字面で明言してしまっています。
古谷先生の作品の中ではまさにこのシガテラのラストシーンがそれであります。「ぼくはつまらない奴になった」・・・このフレーズを含むこのラストだけですべてをかっさらっていきました。そういう意味での点数の高さです。
正直途中何度かリタイヤしそうになりましたが、この作品ほどリタイヤしないで良かったと思う作品もないです。
「どうしちゃったの古谷ぁぁぁ」とその日私は泣きました。
これ以降の作品は非常にパターン化しているのでよほどの古谷マニアで無い限りはオススメできないのですが、年代順でかぞえてこのシガテラまでは絶対に抑えてほしいと思います。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2010-11-05 17:39:35] [修正:2011-02-02 19:26:29] [このレビューのURL]
とかく6巻全体とのり夫、そして賛否両論なラスト(もとい概ねバッシングですが)について語られることが多い本作品。
そして「ぼくらの」と同一に語られることが多い本作品。
確かに主張の根幹は一緒なんだけど、完成度とか洗練さでいうとこちらは完全に破綻している部分があり明らかに「ぼくらの」のほうが洗練されています。
衝撃度だけはこちらのほうが格段に上なんですが。
「ぼくらの」はかなりのよく読まないと分からないけれど、キッチリあらゆる疑問に紙面で回答を与えているのに対して、本作は最後のほうで起こった事柄について明確に紙面で答えてくれていない部分があります。
よく読めば分かるレベルでは鶴丸は何故あのあとホントにツルマルになったのか(コレはよく読めばわかるレベル)ホシ丸のラストはあれどういう意味?(これものり夫のアタリなど竜になることを拒んだりなれなかった人の記述をよく読んでいる人なら)。でもシイナ生き返った明確な理由とかシイナの妊娠については分かる人にしかわからないくらいに不親切です。
多分読んだ人はこの全てが分かっているのだろうと私は信じていますが。
あと漫画家さんでこの作品で語られているような考え主張を心に秘めている人は実はかなり多いですが、その主張について作者自身の態度まで明確に字面で語っているのは私の知る限りでは鬼頭先生と古谷実先生だけです。本作では須藤が学校を辞めるときの会話がもっともダイレクトなものの一例。
ヴァンデミエールの翼のレビューでも触れたのですが、そういった意味でも鬼頭先生と古谷先生はおのずとその後の反比例する動きからの対比してしまいたくなるんです。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2010-11-05 16:31:34] [修正:2011-02-02 19:24:55] [このレビューのURL]