「boo」さんのページ
- ユーザ情報
- 1990年生まれ(性別:男性)
- Webサイト
- http://honetsukitaro.blog.fc2.com/
- アクセス数
- 310509
- 自己紹介
-
「闇夜に遊ぶな子供たち」の続きも読みたいけど、出ても同人になりそういうのは実に残念な話。
ホラーMがなくなったのはやっぱり痛い。
10点、9点…個人的なバイブル、名作。
8点、7点…お気に入りの作品。
6点、5点…十分楽しめた作品。
4点以下…うーんって感じの作品。わりと適当。
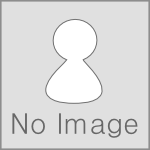
7点 赤ちゃんと僕
いい漫画ですよね。
私が小さい時に姉の本棚にあったこれを読みふけっていたので、かなり思い入れがある作品。短編が連なっている構成で、起承転結がしっかりとしているのですごく読みやすいし読後感がいい。笑えて、泣けて、考えさせられてと括りは少女漫画だけど万人が楽しめると思う。
基本的には小5の拓也と幼児の実、それを見守る父親を中心としたホームドラマ。育児を中心としつつも色んなテーマが取り扱われており、全体的にかなり質が高い(銀行強盗の話だけは好きじゃないけど)。
脇を固める人物として拓也や実の同級生、ご近所さん、父親の同僚など大量の人物が登場するのだが、まあこいつらが揃いも揃ってあくが強い!羅川さんのすごい所はこの脇役達を暴走させずにうまく作品のテーマと絡めていった所だ。何気に大変だったと思う。後半は多少ネタが尽きたのかキャラ頼みの話も見られたが、それでも十分おもしろかった。特に藤井家絡みの話は鉄板ですね。
最終回は泣いた、確かに号泣しましたよ…
でも反則技というか安易というか納得しきれない部分はどうしてもあります。あまりにも唐突だったしありがちなのはこういう漫画の最終回が難しいからというのはあるのだろうけど、羅川さんならもう少しうまくやれた気がするんですよね。
ただ今まで育ててきたキャラだからこそあそこまで泣けたのであってそういう意味では最終回にふさわしくはあったのかもしれません。
誰もが楽しめて、気軽に読める良作品なので時間があればぜひ。
ナイスレビュー: 1 票
[投稿:2011-07-08 00:36:34] [修正:2011-10-27 17:51:39] [このレビューのURL]
7点 坂道のアポロン
ジャズ全盛の1960年代、ジャズを通して繋がる正反対の高校生、薫と正太郎の青春を描く。
まず思ったのは時代背景や絵柄を含めてとにかく古いってこと。しかしこの作品の古さっていうのは恐らくすごく考えて練られたもの。
60年代の固い恋愛観、ビートルズやジャズの大御所に代表される小ネタ、控えめな絵柄、そういう要素が全て純粋で爽やかなキャラクターと素朴な物語を魅力的に見せてくれるのだ。
小玉ユキはこのド直球な青春群像を現代でやってしまうと嘘っぽくなってしまうことを分かっていたんだと思う。この時代でしか、この時代だからこそ成り立つ甘酸っぱさが確実にあるのだから。
素朴な物語を純粋に楽しませてくれるというのは相当力量がないと出来ないし、1960年代を切り取って見せてくれるということを考えてもかなり良い作品。
何といってもジャズの演奏シーンがいい。ここまで音楽してるって作品他にあったかな? まさに音を楽しむという表現が似合う。
私もアポロンを読んでアートブレイキー辺りを聞いたクチなんだけど、色んな音楽を題材とした漫画を読んできたにも関わらず実際にその音楽を聞いてみたのはこれが初めて。クラシックという音楽が限られた枠組みの中で表現を凝らすという素人には分かりにくい凄さだからだろうか。世界を目指して必死、真摯にピアノをやる漫画が多いというのもあるかもしれない。
その点この時代のジャズというのは大衆音楽で、薫達も別にプロを目指しているのではなく単純にやりたいからやっているのだ。すごく身近。また、フリーセッションは私がギターを弾いていて1番楽しいことだし、その楽しさが伝わりやすいものだと思う。だってみんな演奏するのが楽しそうだしジャズが大好きそうだもんね。これは聞きたくなるよ。
しかもこのスタンダードなジャズが片思いにめちゃくちゃ合うんだ。
最近多いぐだぐだなモラトリアムを描く青春ものとは一線を画す作品。異端に見えて王道です。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-08-26 14:30:24] [修正:2011-10-27 17:50:56] [このレビューのURL]
ジョーカーのオリジン話ってこれで何回目なのかな?
キリングジョーク以来のジョーカー創生譚。
オリジンが何回も書かれるってのもおかしな話だけどそれもアメコミの特殊性ゆえ。ある意味全部極めてレベルの高い二次創作みたいなもんだもんなぁ。
ただジョーカーに関しては過去の記憶が記憶が錯乱しているということで、やつのジョークの一部と思えばもはや何でもありだね。キリングジョークと比べてはあれだが、これはこれでまた違ったジョーカーのオリジンを楽しませてもらった。
「彼は“人間存在とはあきらかに異なる化け物”だ。」
「私は人間以下の存在を相手にしているというのか?」
バットマンがゴッサム・シティに現れてから10ヶ月、犯罪者はバットマンに脅えて影を潜め、夜には時に子どもの姿さえ見られるようになった。ブルースは彼のやり方に対する手応えと街の平穏に安堵し、久々の安息を感じていた。
しかし謎の男ジャックの出現が全てを一変させる。ジャックによってブルースが今まで築いた成果、そして彼の自信は崩壊する。そして決断を迫られたバットマンは…。
デニス・コーワンの個性的で見事なアートに魅せられつつも、物語は小気味いいテンポで進み、さくさくと読まされる。バットマンの焦燥、ジョーカーの目覚め、2人の綱引きはどちらに転ぶのか。
何といっても台詞回しがいい。上で引用したような精神科医との会話を代表とした印象的な言葉には唸らされる。
少し違和感を感じたのは、ジョーカーがソシオパスとして描かれているところに所以するように思う。
作中で説明されるように、ジョーカーは、ソシオパスは理解不能というのがこの物語の中での認識だ。いわゆる純粋な悪、人ではなく病原体のようなもの。一つの解釈としておもしろいし、それは別に構わない。ただそれでいてこの物語ではジョーカーを掘り下げようとする部分も感じられる。でもそもそも理解不能を掘り下げるっておかしな話じゃないか?
またタイトルにはマッドメンという言葉がある。複数形、マッドメンというなら彼らは同じく狂気の側にいるはずだ。
でも私がこの作品から感じたのは前述したように理性と狂気の両端にバットマンとジョーカーが立って綱引きしている姿。引きずりこまれそうにはなっても同じ側にはいないように感じられる。
個人的にはそういう風に疑問に思った部分もありつつも、わりかしシンプルに楽しめるジョーカー誕生譚。爽快さもあれば、ヒーローゆえの哀愁をも漂う男の物語。
アザレロの「JOKER」とセットでジョーカー好きならおすすめしたい。キリングジョークを先に読んでおいて欲しくはあるのだけど。
ラバーズ&マッドメンの先にキリングジョークの結末があるかもしれないな、なんて想像するのも興味深い。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-10-27 00:39:23] [修正:2011-10-27 00:47:59] [このレビューのURL]
7点 虫と歌 市川春子作品集
奇才・市川春子の第1作。久々にアフタらしい鮮烈な才能を感じた。
アフタヌーンは昔から良い意味で突飛な漫画家が多い。ただ植芝理一、弐瓶勉、木村紺あたりが最近丸くなったなーと感じている。尖ったまま変化するのは難しいし、その是非は読み手次第だから悪いことではないのだろうけど何となく寂しい。
そんな風に感じていた中で登場した鮮烈な奇才、市川春子はかなり楽しみにしている作家さん。
虫と歌はSF風味の4話からなる短編集。人とそれ以外のものとの交流を描く。
どの話もとても「痛い」。少しずつねじれていて、変質的で、痛すぎる。たまらない。
個人的なベストは表題作の虫と歌。すごいよ。痛いよ。
その作風から市川春子は高野文子とよく比べられるし、人によってはパクリだと罵られることもある。実際私も似ているとは思うし、本人も高野文子を尊敬しているそうだ。
ただ、考えてみて欲しいのは高野文子の後を追うというのがどんなに難しいことであるかということ。そもそもどんな作家だって誰かしらから強く影響を受けている。市川春子は表面上ではなく、曲がりなりにも自分のものとして高野文子を取り入れられているように思う。
私が虫と歌の好きな所は、世界を描く熱心さ。
ただその熱心さというのは分かりにくさと表裏一体のものでもある。なぜなら彼女は彼女の世界観を描くことには熱心でもそれを読者に説明することには熱心ではないからだ。だから最初読んだ時はあまりに難解に感じられる。
でもそれはあくまで難しいであって不可能ではない。読み解くのに必要な材料は作中に最低限ではあるにしろ揃っているし、その読み解く作業が楽しいのだ。
分かりにくい、不親切だと作家を非難するのは容易い。そりゃあ作者から読者に歩み寄ってもらうのもいい。でも時には読者の方から作者の世界に近づこうとしたっていいじゃない。そうすることで他の漫画では感じられないものがあるのだから尚更だ。
漫画好きなら高野文子含め、好き嫌いは分かれるにしろ一読を勧めたい作品。その奇才に驚愕する方もいるだろうし、大好きな作品になる方もいるだろう。こんな漫画もあっていい。あって欲しい。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-09-13 12:54:51] [修正:2011-10-26 00:16:52] [このレビューのURL]
7点 さんさん録
こうの史代の作品にハズレはないなぁ。何でそんなに安定感があるのかと考えた時、核にあるのはさんさん録や長い道に分かりやすい温かみじゃないかと思う。
参平さんみたいな老後がいいなと思うのは別に家事がしたいとかではなくて、老いても何かしら存在意義を感じていられたら生きている喜びが感じられるのではないかなってこと。
そりゃまあ趣味に生きるのもいいのだけど、他人に必要とされるのは人として大事な気がする。孫の面倒を見るのだって何でもいい、生活に張りがあれば参平さんのようにそれなりに楽しくやっていける。
妻に先立たれた参平は息子に勧められるまま、息子夫婦とその小学生の娘との同居を開始する。成り行きで参平は家事全般を担当することに。妻のおつうが残した「奥田家の記録」を頼りに参平の主夫生活が始まった。
参平じいさんのどたばたな生活を見ているのは楽しい。家事を「奥田家の記録」から学ぶ参平、時には、いやかなり頻繁に勘違いをやらかす参平、かなり変人な孫との微笑ましい?交流、時にはどきどきするロマンスもあったりして参平さんの老後はなかなかに忙しい。
この忙しいというのがすごく幸せな忙しさに感じられる。老後の生活に張りがあるというのは多分こういうことだ。
参平の家族も本当にいい家族。ちょっと現代的なライトさもありつつも優しい息子、もはやこうの作品常連とも言える天然な可愛い奥さん、そして気持ち悪いもの好きの変な孫。それぞれにとても愛おしい。
ちょっと興味深いなと思ったのは参平さんが常に妻・おつうを意識している所。参平さんは彼女に恥ずかしくない行いはしまいと思って生活している。
これってアメリカの「常に神は見ている」精神にすごく似ている。人の目はもちろん誰だって気にする。でもアメリカ人は誰も見ていなくても神が見ているからという意識はすごく大きいらしい。別に宗教に限らず、何かに恥じない生き方というのは一つの理想かもしれない。窮屈とも言えるかもしれないけれど。
こうの史代といえば夕凪の街 桜の国やこの世界の片隅にという名作のイメージが強いと思う。でもやっぱり何度も読み返して楽しい気分になれるさんさん録のような作品だってすごくいい。
本当にこんな老後を送りたいと思わせてくれた。まだ私はそんな年じゃないけど、羨ましいなぁ。
ナイスレビュー: 1 票
[投稿:2011-10-25 00:37:33] [修正:2011-10-25 00:38:14] [このレビューのURL]
8点 犬を飼う
谷口ジローの私小説的漫画の傑作。犬を飼ったことのある人にとってはたまらない。
彼は妻と二人暮らし。子どもはいない。彼らはタムという年老いた犬を飼っている。
「犬を飼う」はタムの最後の一年を描く物語。日に日に年老い、体が弱っていくタム。彼らはタムのことを考えて色々と尽力してサポートするが、死へ近づくのは止められない。そしてとうとう避けられない日がやってくる。タムとの暮らしは2人に何を残したのか。
「そして…猫を飼う」からの3編はタムの死後、彼らが猫を飼うことになったきっかけ、その後の日常が描かれる。ペットを飼うことで得られるもの、苦労もある一方そのかけがえのない喜びが語られていく。
「約束の地」は前者2つと話が一変、家族がいるもののヒマラヤへどうしても惹きつけられる男の物語。
谷口ジローはバンド・デシネに大きく影響を受けた作家ということはよく言われる。その影響だろうか、一コマあたりが濃く、あまり遊びのコマが見られない。「犬を飼う」ではその緊迫感が話の密度を上げるのに一役買っている。
この犬を飼う、私にとってはたまらない話だった。というのも私が子どもの頃に家でも犬を飼っていて、その最期はどちらかというと何もしてやれなかったような後悔があったから。谷口ジローとその奥さんはまるで自分の親を介護するように、タムの世話をする。その心労のために会話も少なくなったりする。タムは家庭に良かれ悪しかれ影響を及ぼす家族の一員なのだ。
心打たれる名編だが、自分の過去のペットに対してかなり忸怩たる思いになった。でもここまでする覚悟がなければ動物を飼うべきではないのだろう。
で、そんな多少暗い気分を吹き飛ばしてくれたのが「そして…猫を飼う」からの3編。
ここには動物と共に暮らすことの喜びが詰まっている。世話をする苦労を超えるものがある。その中の「三人の日々」はあまり猫は関わってこないのだけど、その記憶をを思い出すときに確実にその傍らに猫達はいると思う。ペットってそんな存在だよね。
「約束の地」は山、何といっても山。神々の山嶺でも存分に見られる、山の迫力、魔力は圧巻だった。写実的に上手い作家なのはもちろんだけど、それだけではこうはいかない。
秀作ぞろいの谷口ジロー作品だが、これもまた良い作品。図書館で借りたものだけど、これは買って手元においていきたい。
そして何だかんだいつかまた動物を飼いたくなったのだった。自分以外の世話も出来るようになったと思えた時に。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-10-21 00:22:43] [修正:2011-10-21 00:28:50] [このレビューのURL]
6点 ヴィリ
ヴィリは舞姫(テレプシコーラ)の第一部と第二部のつなぎとして描かれた。テレプシコーラに隠れて今一目立たないけどこれも良い作品。
東山礼奈は43歳になるが今でも日本でトップクラスのバレエダンサー。高校生の娘を持ち、バレエ団を経営する身でもある。
一時休養していた彼女であったが復帰作としてジゼルの全幕を発表することに。
バレエ団のパトロンも現れ、恋の予感も芽生えてと万事順調に思えた彼女であったが…。
「ヴィリ」とは結婚直前で亡くなった女性が精霊になったものということ。礼奈が踊る予定のジゼルにも登場する。
このタイトルから何となく内容とテーマが見えてくると思う。
テレプシコーラの第一部を見た人は分かると思うが、山岸涼子は構成がとても上手い。それは先が読めないのに後から読むと必然的だと感じられるということ。
先の展開へのきっかけというのはもちろんあるのだけど、山岸涼子の場合あまり伏線と言うのが似つかわしくない。それは勘違いであり見落としでもある。確かに提示されているものなのに、登場人物と一緒に読者まで間違ったりスルーしてしまうのだ。ゆえに事件は降って湧いたような気がするのだけど、確かに話はつながっているし、つながりがあるからこそ後悔が真実味を帯びる。
このヴィリでもそれは変わっていなくて、満たされた状態から奈落の底に落ちる話を山岸涼子は痛いほどに巧みに描く。
ジゼルというのはこの作品の解釈では、貴族の戯れの恋としてジゼルをもてあそんだアルブレヒトをヴィリとなったジゼルが許す物語だ。
作中で礼奈は彼を許せるジゼルを踊りたいと言う。愛とは許すことなのだと。
「許す」というのは一つのキーワードだろう。
辛い過去は許さないと、折り合いをつけないとその人自身を蝕んでしまう。どうしても折り合いがつかなくて鬼や化け物になってしまう童話や物語をどんなにたくさん思いつくことか。バットマンやジョーカーだって、過去を切り離せないからこそ異形の姿になってしまう。先に進めなくなってしまう。
ヴィリはそういう昔からある「許し」をモチーフにした話を現代的に分かりやすくリファインした作品と言えるだろう。許すことの意義が丁寧に描かれている。
定番だからこそ、山岸涼子の確かな実力が際立つ良い作品だった。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-10-19 23:26:06] [修正:2011-10-21 00:28:14] [このレビューのURL]
6点 日本の兄弟
日本の兄弟も青い春と同様に松本大洋の負の部分が発揮された作品だ。
でもこちらの方はともすれば抜けられずに死んでしまいそうな、そんな暗いものがある。
「何も始まらなかった一日の終わり」シリーズでは死を見つめている。
死に向かって飛ぶ青年。
初めて死を意識した少年。
死を目前にした男の回想。
それはLOVE2 MONKEY SHOWでも変わらない。
「死」は日本の…シリーズから転じて「虚無」になる。
あきらめ、都市の中での孤独感、疎外感、松本大洋の線は抽象的な寂しさを表すのが上手い。
そういう虚無感から生まれたファンタジーが日本の兄弟だろうか。そこでは勉強に意味はない。クジラが雨を降らすユートピア。
頑張って言葉で表そうとしてみたけど、難しい。それはやはり松本大洋がはっきりとしない感情を漫画にしたからかもしれないし、まだこの時は表現力がテーマに追いついていない部分もあるのかもしれない。
同一ではないが、Sunnyにも登場するハルオやはげまし学級という名前もこの作品には見られる。抽象的にならざるを得なかったのだろうか?
ダイナマイツGON GONだけはこの短編集の中での位置づけがよく分からない。わりと明るくて単純な話な気がするので他の短編とのつながりがあまり見えないのだけど。
私が一番印象深かったのは「何も始まらなかった一日の終わり」のハルオ編。
私は小さい頃、自分が初めて死を意識した日を覚えている。きっかけは忘れたが、両親も、そしていつかは自分も消えてなくなると知ってしまったことを覚えている。あまりにもショックで吐いたことを覚えている。
そういうある意味原始的な死への恐怖がこの短編集にはある。そして死は虚無と隣り合わせだ。
ちょっと怖くなるような、病んでしまうような、日本の兄弟はそんな作品。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-10-19 00:22:02] [修正:2011-10-19 00:27:43] [このレビューのURL]
7点 青い春
松本大洋の青すぎる春。
松本大洋初見だとかなり取っ付き難く感じるかもしれない。もしかしたらピンポンや鉄コンを既読の方であっても。
度胸を示すために簡単に命を懸ける。
ロシアンルーレットで生を感じる少年達。
取り返せるものならば…打てども打てども終わらない夏。
ヤクザの世界に飛び込む木村と誘い入れる鈴木。
飛べなかった少年は糞ったれな現実にピースする。
繰り返されるだべり。噛み合わない会話。
終わらない悪夢と報われない思い。
青春の鬱屈とした全てがここに詰まっている。
「誰か俺をこの檻から出してくれ!」
少年達の心からの叫び。閉塞からの開放を求める思い。出口は無い。
だからこそ青い春を読むときは息が詰まる。でも思い返してみれば、あの頃はそんなだった気がする。
青い春は松本大洋が奏でる青春のブルースだ。ただ本来のブルースというのはやりきれない現実や思いだからこそ明るく歌い上げる意外にノリのいい音楽なのだけど、ここにはひたすら陰鬱なものしかない。
でもこの暗く、青すぎる抑圧があったからこそ鉄コン筋クリートやピンポンで見せた解放がある。
青い春という作品は松本大洋のイニシエーションだったのかもしれない。トンネルの中が暗いのは当たり前なのだ。
松本大洋、この時未だ26歳。そのあまりにも青く鮮烈な才能が垣間見える。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-10-18 01:41:38] [修正:2011-10-18 01:41:38] [このレビューのURL]
7点 月のパルス
オカルトを代表とする小道具の使い方がすごく上手い。くらもちふさこの隠れた秀作。
主人公が運命の男(女)に出会う物語、というと少女漫画の一つの典型例かもしれない。
月のパルスもそういう話なんだけど、そこはくらもちふさこですよ。一筋縄ではいかないかなり癖のある作品に仕上がっている。
父親に殴られた衝撃が原因か、16歳の高校生宇太郎は異世界や人に憑いているものが見えるようになってしまう。あることで同年代の女の子、紀は宇太郎と知り合い、恋をするが、宇太郎は彼女は頭の上に黒い憑き物を見ていた。
紀には月子という友人がいる。しかし紀が恋をした男の子はいつも月子を好きになってしまうのだ。だから彼女は月子と宇太郎を近付かせないと決意していたが、彼はしばしば異界の奥や夢の中で月子の姿をそれと知らずに見るようになり…。
最初の方をちょっと読めば嫌でも分かってしまう。ああ、宇太郎は月子に出会うんだなと。
主人公が運命の人と出会う、こういう物語ではほぼ100%その恋の障害となる人が現れる。ほとんどの作品でそういう存在というのは本命の2人を盛り上げる刺身のツマでしかないのだが、くらもちふさこは刺身のツマ、紀をも主人公格に持ってきてしまう。
視点の変更、紀の気持ちが哀しくて切ない。シンプルな話なのに一味違う。
これだけでも十分おもしろくはあるのだけど、それだけでは終わらないのがくらもちふさこ。
2回読むとまた違うものが見えてくる。鍵となるのはおばあちゃん。ただ呆けていたと思っていた言動、そしてミスリード、これはただ運命の出会いといえるのか?
以下ちょっとネタバレなので未読の方は見ないほうがいいかも。
ちょっと違う点から考えてみる。
題名である月のパルス。単純に月子の波動が宇太郎を捉える話としてもいい。また紀(きの)はのり(糊)とも読める。なのでのりが月とうた(パルス)の間に挟まる障害物でありくっつける存在であることを示唆しているという穿った見方も出来る。
2度見た後だとまた変わってくる。魔法のあめ、前世…月ちゃんは憑きちゃんなのだ。憑きの波動?それが運命?
正直震えた。下手なホラーよりよっぽど怖いよ
単純な物語に二重三重と意味を持たせるくらもちふさこには感服するしかない。もはや私にとっては怪作と言えるほどだけど、人によって色んな見方が出来ると思う。
読者によって異なる受け取り方が出来る漫画、多分そういう作品はすごくいいものだ。
ナイスレビュー: 0 票
[投稿:2011-10-15 00:55:11] [修正:2011-10-15 00:55:11] [このレビューのURL]
月別のレビュー表示
- 月指定なし
- 2007年06月 - 1件
- 2007年07月 - 7件
- 2007年09月 - 1件
- 2007年10月 - 1件
- 2007年11月 - 2件
- 2008年03月 - 1件
- 2008年07月 - 3件
- 2009年01月 - 2件
- 2009年03月 - 1件
- 2009年05月 - 1件
- 2009年12月 - 1件
- 2011年06月 - 2件
- 2011年07月 - 33件
- 2011年08月 - 28件
- 2011年09月 - 26件
- 2011年10月 - 36件
- 2011年11月 - 20件
- 2011年12月 - 12件
- 2012年01月 - 21件
- 2012年02月 - 8件
- 2012年03月 - 5件
- 2012年04月 - 10件
- 2012年05月 - 7件
- 2012年06月 - 7件
- 2012年07月 - 4件
- 2012年08月 - 1件
- 2012年09月 - 8件
- 2012年10月 - 3件
- 2012年11月 - 3件
- 2012年12月 - 3件